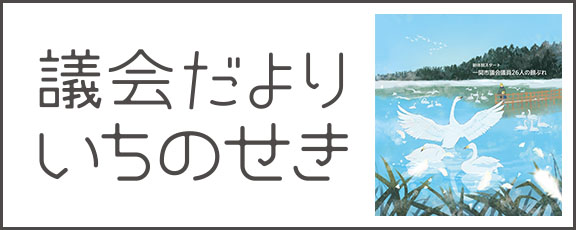道の変遷、時代とともに 県立博物館テーマ展 奥州、宮古街道にスポット【岩手】
県立博物館のテーマ展「岩手の往来~道路のいま・むかし~」は、盛岡市上田字松屋敷の同館で開かれている。道路網形成の礎になった奥州街道と宮古街道(閉伊街道)にスポットを当て、約130点の資料を通じて現在までの道路、さらに未来へ向けての道路の姿を紹介している。5月6日まで。
序章を含む5章構成で、江戸時代の参勤交代や蝦夷(えぞ)地開発、ロシアからの蝦夷地防衛のための往来に使われた奥州街道、今も宮古盛岡横断道路として開発が進み災害からの復興を担うかつての宮古街道を中心に掘り下げた。
参勤交代の往来の様子を伝える「南部藩参勤交代絵巻」(江戸時代)は幅28センチ、長さ29メートルを超える大作で、総勢650人の上る行列の順序や衣装、道具、立ち姿などが細かく描写された貴重な資料。向鶴の金蒔絵(まきえ)が施された南部家伝来の陣笠(がさ)や、大名行列の先頭に立てたと伝わる南部家家宝の槍(やり)なども並ぶ。
下北・津軽半島から千島、樺太までを描いた絵図「蝦夷地図」(江戸時代)は、江戸時代中期の蝦夷地開発、また末期のロシアからの蝦夷防衛に利用された奥州街道の歴史がうかがえる。盛岡近辺以南の宿場をたどる大正・昭和初期の地図もある。
宮古街道は盛岡城下の鉈屋町地内で遠野街道から分岐し、簗川・区界峠を越え閉伊川沿に宮古へ至る難所続きの道筋。「御城下ヨリ宮古迄街道図面」(江戸時代)は「▲」の記号で難所を記し、普請を終えた難所の記号近くには「スミ」と記され、距離を短縮するために難所の改修工事が進められたことが分かる。
1981年の台風15号で増水した閉伊川の氾濫で流され、トンネルの開通でわずか17年という短い期間で役割を終えざるを得なかった旧国道106号に残された「與部沢橋」、現在工事中の「宮古盛岡横断道路」の整備効果なども紹介されている。
序章では県内各地の鳥瞰(ちょうかん)図や観光案内を集め、岩手の恵まれた絶景や歴史的建造物、海産物などが詳細に描かれた県観光協会発行のパンフレットの原画「岩手県観光鳥瞰図原図」(1937年、縦78センチ、横408センチ、絹本着色)などもある。
主任専門学芸調査員の薗田貴弘さんは「道路は命をつなぐもの。先人の積み重ねられた苦労が今につながり、未来へ生かそうと努力している人がいる。そんな道がどうなるのか未来に思いをはせながら見てほしい」と話している。