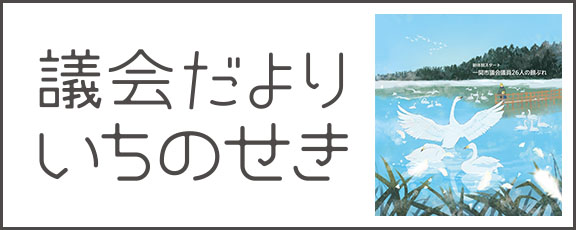重なり合う科学と信仰・呪術 一関市博物館テーマ展「天体と時間の文化史」
一関市厳美町の市博物館でテーマ展「天体と時間の文化史」が開かれ、一関藩と仙台藩に関する資料を中心に85点が5章構成で展示されている。江戸時代の人々が天文の知識を科学だけでなく呪術、占いなどさまざまな形で用いていたことが分かる奥深い内容になっている。3月21日まで。
展示構成は▽渋川春海と仙台・一関▽佐竹義根とその周辺~天文道を継ぐものたち▽科学への道のり~和算・蘭学▽天体・時間といとなみ▽江戸時代の陰陽師。
前半は、日本人による最初の暦「貞享暦」を完成させた天文暦学者・渋川春海から一関藩初代藩主・田村建顕への書状など、春海と仙台藩・一関藩とのつながりが分かる書物が並ぶ。磐井郡出身で春海の学問を継承し仙台藩で広める役割を担った佐竹義根とその弟子たちに関する記録や道具も見られる。義根は一関市大東町出身で仙台藩の儒学者だった芦東山と親戚関係にあり、義根との交流や天体現象について記した東山の日記も展示されている。
中盤から後半にかけては天球儀や算額、和製望遠鏡、天体図、暦、香時計などが集められている。1843(天保14)年の大彗星(すいせい)を描いた図や、50(嘉永3)年に陸前高田市へ落下した日本最大の隕石(いんせき)などもあり、彗星が吉凶の兆しと捉えられていた様子が伝わる。災害や吉凶を占い、天体観測などを行っていた役人・陰陽師にまつわる資料からは、陰陽道に基づく呪術や占いを人々が生活に取り入れていたことが分かる。
同展担当の髙橋紘学芸員は「天体や時間の知識は現代だと科学のイメージが強いが、江戸時代ぐらいまでは信仰や呪術が重なり合うものだった。今回はそこに目を向け、当時の人たちが天体や時間の知識を生活にどう取り込み、学んでいたのかを紹介した」と説明する。一関藩や仙台藩は天体や時間に関する学問が盛んで、磐井郡の関係者にその中心を担う人物がいたことにも注目したといい「最先端の科学が入ってきても呪術や占いなどの側面が失われなかったところに人間らしい精神性が感じられる」と見どころを語る。
2月5日には菊池勇夫館長の講座「暮らしのなかの暦・占い~南部絵暦と東方朔」が開催される。定員50人で、事前申し込みが必要。来月5、19日と3月4、18、19日には同館学芸員による展示解説会が開かれる。
問い合わせは同館=0191(29)3180=へ。
電子新聞momottoで紙面未掲載写真を公開中