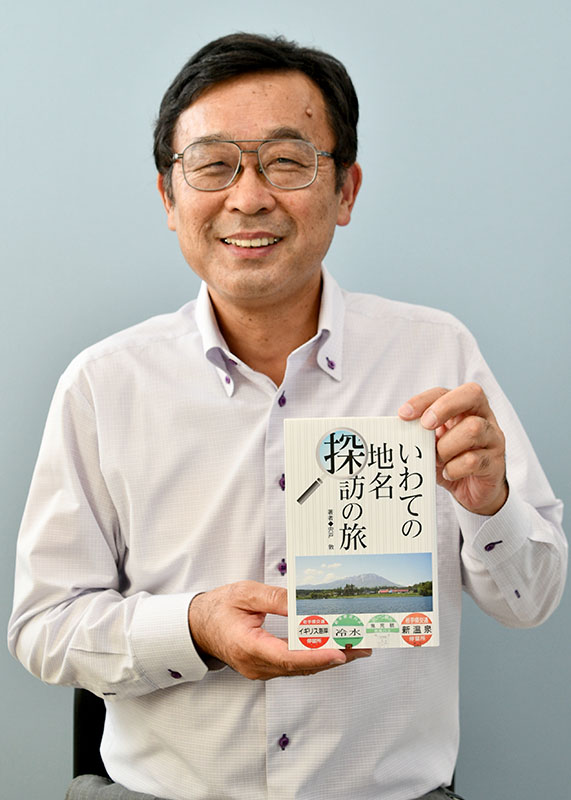“土地の履歴書”一読を 県内約190地名の由来紹介 宍戸さん(胆沢)書籍出版 市文化財保護調査員【奥州】
奥州市胆沢南都田字国分の市文化財保護調査員宍戸敦さん(62)は、長年の調査をまとめた「いわての地名探訪の旅」を出版した。時間を見つけて40年以上、県内を訪ねて調べた約190の地名の由来を紹介。宍戸さんは「地名は『土地の履歴書』。誰もが見てその通りと思って名付けられるため、名前負けもない。一人でも多くの人に興味を持ってほしい」と一読を勧めている。
宍戸さんは県文化財保護指導員も務める。学生時代に東京都で暮らし、歴史を感じられる地名が身近にあったことから地名への関心を育んだ。20歳ごろから県内の地名の調査を始め、「角川日本地名大辞典・岩手県」(角川書店)、「岩手の地名」(県地名研究会)などの執筆者に名を連ねている。
「いわての地名探訪の旅」(B6判、215ページ)は、初めて単独執筆した書籍。事前に文献に当たり、現地を訪ねて十分に調べが付いた地名を県内7地区に大別して解説。可能な限り略図を添え、土地の来歴を紹介している。花巻・北上、胆江、一関各地方の章もある。
このうち奥州市の「桜ノ目」(水沢)と「蛇の鼻」(前沢)は、北上川舟運の名残。「桜ノ目」は航行の目印となった桜の大木があったことに由来する。「蛇の鼻」は大きく川がカーブし、流れも急な難所。「鼻」は台地の突端を指し、県内にもほかに含まれる地名が残っている。
また一関市大東町の「魚集(よまつべ)」は、「うお・あつめ」。近くの砂鉄川にサケが遡上(そじょう)していたことにちなみ、「魚(うお)」が転じた方言の「よ」が使われているという。
「地名は裏に歴史的な意味や出来事があり、知ることで暮らしを豊かにしてくれる」という宍戸さん。堤防の決壊した場所に付けられる「押切」など、過去に起きた災害を記録しているものもあるといい、「危険な場所を教えてくれる」とも。
世代交代や開発で古い地名や地元の伝承が失われていくのを目の当たりにしており、「多くの人に地名の由来を知り、親しみと興味を持ってもらうことがスタートかと思う」とし、調査を続けている。
税込み1980円。県内の書店で購入できる。問い合わせは発行の合同会社ここみーる=019(656)9998=へ。