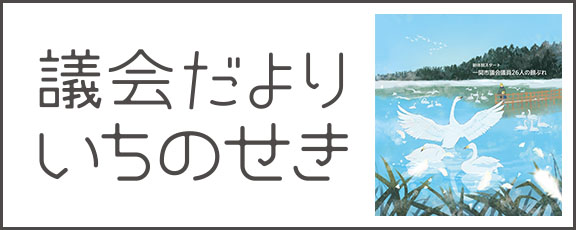認定へ現地調査 束稲山麓地域 専門家が聞き取り 世界農業遺産
一関、奥州、平泉3市町にまたがる束稲山麓地域の国連食糧農業機関(FAO)による世界農業遺産認定申請に係る承認と、農林水産大臣による日本農業遺産認定に向けた専門家の現地調査は13日、行われた。書類1次審査を通過した「災害から生命(いのち)と生活(くらし)を守り未来へつなぐ束稲山麓地域のリスク分散土地利用システム」を実際に確認するもので、同システムの構成要素となる場所を訪れ関係者への聞き取りなどを実施。今後は12月の2次審査会(プレゼンテーションなど)を経て、2023年1月には日本農業遺産の認定と世界農業遺産への認定申請に係る承認の是非が決まる。
世界農業遺産等専門家会議の武内和彦委員長(地球環境戦略研究機関理事長)、市田知子委員(明治大農学部教授)、小谷あゆみ委員(フリーアナウンサー、農業ジャーナリスト)の3人と農水省の担当職員が訪れ、金山棚田(一関市舞川)、農事組合法人アグリ平泉ブドウ園地、女石ため池(以上平泉町長島)、イロハモミジの森、月山松(以上奥州市前沢生母)などを調査。一関市狐禅寺の北上川学習交流館あいぽーとでは、調査開始に先立ち申請団体となる束稲山麓地域世界農業遺産認定推進協議会会長を務める平泉町の青木幸保町長が「災害から命と暮らしを守るシステムは、地域の活性化だけでなく後世に伝え、未来につなげていく価値がある」と認定の必要性を語った。
館内にある現地の航空写真を用いた概要説明も行われ、同協議会委員の丸山安四さん(87)=同町長島字小戸=は「この地域では昔からヤギ(低平地)とオカ(山麓地)で異なる作物を栽培することで、災害の影響を少なくする工夫が続けられてきた」と説明。委員からは、治水事業の現状などについて質問があった。
同協議会が認定を目指すシステムは、肥沃(ひよく)な土壌の半面、洪水害に見舞われる北上川沿いの低平地と、干ばつや土砂災害がある山麓地を分散所有して異なる作物を組み合わせることで、他に例のない災害リスク低減の工夫が行われている点などが特徴。18年度に初めて提出した申請書は1次審査を通らず、20年度の再挑戦は2次審査で落選しており、今回が3度目の挑戦。
世界農業遺産は、地域固有の自然や環境、伝統文化が反映された農業文化や風景を後世に残すためFAOが認定しているもので、世界22カ国67地域、日本では13地域が認定されている。