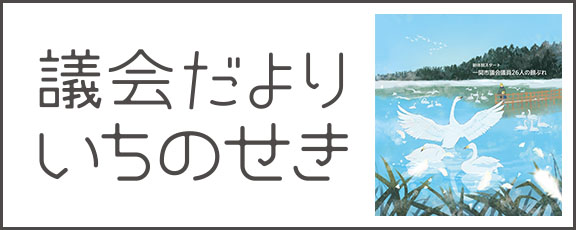土蔵に戦前の花嫁衣装 29日から一般公開 酒のかんりょう【一関】

一関市地主町の酒のかんりょう(神崎良一代表)が解体した土蔵の中から、戦前の打ち掛けや振り袖、帯が発見された。昭和初期の花嫁衣装として保管されていたとみられ、1947、48年のカスリン、アイオン両台風による水害も乗り越えて残されていた。当時の高度な技術を使って作られて保存状態も良く、29日から開かれる木目込人形展に合わせて初めて一般に公開される。
土蔵は現在の店舗北側にあったが、岩手・宮城内陸地震や東日本大震災の影響で損傷が激しかったことから、やむなく解体を決断。2021年秋に解体作業を終えたが、その際に茶箱30箱ほどが見つかったという。その中の一つに風呂敷包みがあり、広げたところ花嫁衣装だった。
衣装は、神崎代表の祖母に当たる旧姓三浦ユキさん(故人)のものとみられる。宮城県若柳町出身のユキさんは同店前身の食料品卸問屋「神良商店」を営んでいた神崎家に1929(昭和4)年に19歳で嫁いだ。三浦家は地域の豪商として代々造り酒屋の大場屋酒造店として繁栄し、「宮城鶴」という日本酒を醸造・販売していたという。
発見された打ち掛けには宮城鶴にちなんでか、鶴のつがいがデザイン違いで6組あしらわれている。難易度が高い技術の刺繍(ししゅう)で作られていることが分かる。
地主町はカスリン、アイオン両台風で水害に見舞われ、神良商店でも家人が土蔵の屋根に上って難を逃れたとされる。土蔵の壁にも高い位置まで水害の痕跡が残されていたが、茶箱は2階の上部に置かれていたため、流されたり浸かったりすることがなかったとみられる。水害で写真などは全て流されており、この花嫁衣装についてもユキさんから知らされていなかったといい、見つかった際は家族全員が驚いたという。
これらの花嫁衣装は、29、30の両日に同市大手町の一関文化センターで開かれる東京木目込人形師範会杜纓会一関支部の創立25周年記念作品展に合わせて公開される。神崎代表は「93年間眠っていたもので、昔の人の技術に触れてもらい、若い人たちにこういう仕事に携わってみたいと思ってもらえればうれしい」と語っている。
同展の開催時間は29日は午前10時~午後5時、30日は3時まで。