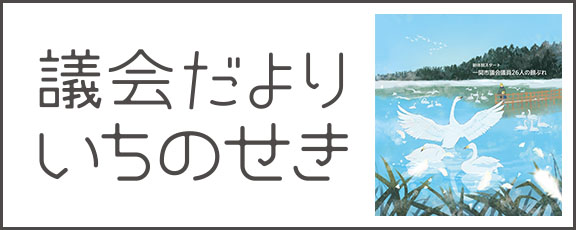無病息災 安寧願い 白木野人形送り【西和賀】
西和賀町の白木野地区に伝わる厄払いの伝統行事「白木野人形送り」は19日、同地区内で行われた。地域住民が侍をかたどったわら人形を担ぎ出し、新型コロナウイルスの終息や一年の安寧を願った。
集落の外れに人形を運び、外から災厄が入ってくるのを防ぐのが狙いで、疫病が流行した江戸時代中期に始まったと伝えられ、毎年1月19日に行われている。終戦前後までは旧湯田町の各集落で行われており、1982年に同町の無形民俗文化財に指定された。
白木野公民館で行われた人形作りでは、住民ら15人ほどが稲わらでつくった頭部や手足、かみしも、木の枝の刀などを組み合わせて縛り、たけだけしい表情を添えて仕上げた。
住民は完成した1メートルほどの武者人形を担ぎ、行列をつくって同公民館を出発。晴天の下、アマチュアカメラマンらを引き連れながらほら貝や太鼓を鳴らして約800メートル練り歩き、隣の集落との境付近にある木に人形をくくり付けて手を合わせていた。
約20年ぶりにほら貝を担当したという中島大樹さん(32)=同町白木野=は「無病息災の願いを込めて一生懸命吹いた。世界中で疫病がはやっているが、感染が落ち着き、マスクを外せるようになればいい。立派な人形ができたので、見守られながら一年間より良い生活を送っていきたい」と語った。
電子新聞momottoで紙面未掲載写真を公開中