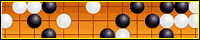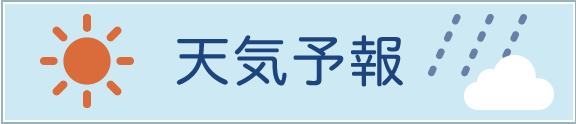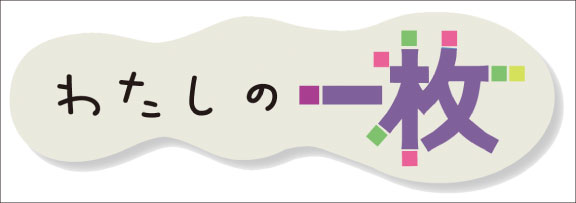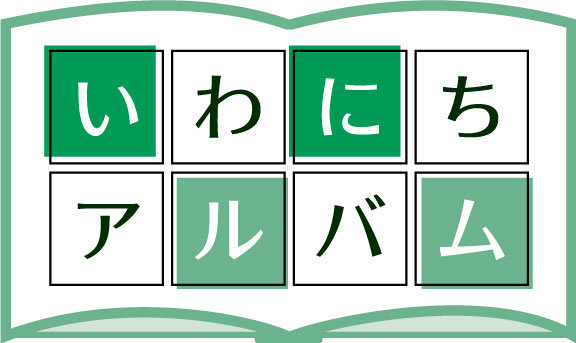付きまとう罪悪感<24>
「罪悪感が付きまとっている」と、Lさんは言う。
Lさんは40代の女性。30代までに幾つかの仕事に就いたが、いずれも長続きしなかった。聡(そう)明(めい)であるが、感受性が強く繊細なので、「他者のいろいろな面が見えると消耗してしまう」のだという。ひきこもり始めてから10年近くになる。
「その罪悪感はどこから?」と私は尋ねた。
「まずは、同居している母に悪くて…」
彼女は現在、70代の母親と2人暮らしだ。母の年金と亡き父の遺産、それと自身の貯金を少しずつ使いながら暮らしている。
母親は初めこそ娘のことで相談に出掛けたり、何かできることはないかと気をもんでいたが、いわく「疲れたのか、諦めたのか」、今は特に何も言ってこないのだそうだ。
「母も傷ついたと思います」と彼女。「以前どこかの相談に行った時に育児についてしつこく聞かれて、まるで責められているようだったと言っていました。それに親戚にも嫌みを言われたらしく、今は付き合いをやめてしまったんです」
口調には、怒りも帯びてきている。
「近所の人たちの目も嫌で、外に出るのも苦痛です…」。そして、「世間は、ひきこもりに冷たいですよね」。目に涙を浮かべた。
罪悪感という言葉を本人たちはよく使う。「家族に負担をかけているから」「仕事をしていないから」等々。だが、ひきこもることは罪だろうか。そうならざるを得ない状況で苦悩している彼らは悪だろうか。
「社会的排除」という言葉がある。特定の人たちをその社会が排除してしまう構造のことだ。社会活動の中で困難に当たったときにひきこもることは自己防衛であり、人権の発動の一つであるだろう。だが、社会の認識不足、努力不足、不作為によって、彼らはさらに追い込まれている。
Lさんの愛読書は宮沢賢治だそうだ。「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」(農民芸術概論綱要)。理想郷イーハトーブは遠いのだろうか。
(終わり)
個人情報保護のため、事例は再構成してあります。(構成、そらをみた会代表・阿部直樹)