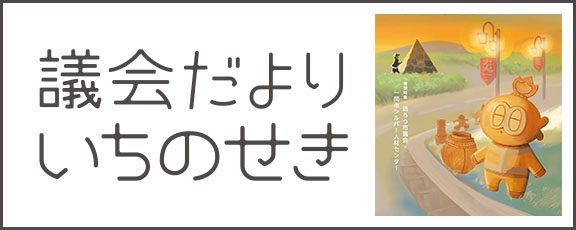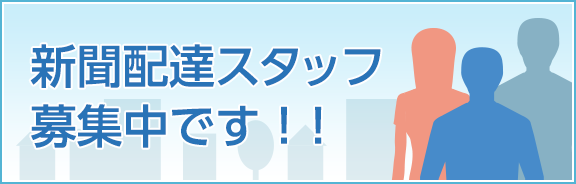つなぐ鉄路 北上線全線開通100周年(上)
北上市と西和賀町、秋田県横手市をつなぐJR北上線は15日、全線開通100周年を迎えた。奥羽山脈をまたぎ岩手、秋田両県を結ぶ移動手段として物流、観光など地域経済を支え、重要な役割を果たしてきた。地域をけん引した同線の1世紀を振り返り、課題となっている利用促進策について考える。(3回続き)
鉱山が敷設の原動力に
和賀町史談会などによると北上線の前身、「横黒線」の建設運動は1890年代、現在の北上市に本社を置く陸羽鉄道会社が発起し始まったが、日清戦争直後の財界不況の影響もあり着工に至らなかった。1900年代に入り鉄道の早期敷設を目指して黒沢尻町が熱心に運動を展開し岩手、秋田両県議会議長も政府・国会に意見書を提出したが具体化しなかった。
それが14年、秋田県横手町有志が政府関係者に陳情したのを機に再び日の目を見た。16年2月の帝国議会衆議院本会議で横黒線の事業化を含む鉄道敷設法改正が審議された際には、「鉱山が驚くべし260幾つあるのである」「この鉱山が金、銅、鉄、かようなものである」と提案理由で守屋此助代議士が力説。当時は第1次世界大戦中、世界的に金属鉱物の需要が高まる中で、鉄道敷設により鉱物の運送費が安くなり、「国家的な利益」と大多数の賛成で可決された。
工事は横手、黒沢尻の東西両方向から進められ24年11月15日、大荒沢―陸中川尻間の開通により全線開通を見た。全長1500メートルの仙人トンネルは同線最大の難工事だったとされる。
江釣子、藤根、横川目各駅周辺の街道沿いには民家や商店、郵便局、駐在所、開業医が立地して町村が形成された。岩沢、和賀仙人、大荒沢、陸中大石、陸中川尻の各駅は、同線敷設の大きな原動力となった鉱山を後ろ盾として鉱山関係者で集落ができ、にぎわうようになった。人と物が流れる動脈として欠かせない路線となった。
同史談会会長の菊池國雄さん(88)は「岩手、秋田を結ぶ最も古い鉄道として、沿線の鉱産資源や森林資源、観光資源の開発と地域住民の利便性向上に果たした役割は計りしれない」と説明。高校時代、横黒線を通学で利用した兒玉智江さん(83)は「毎日ぎっちり混んでいて立っていなければならなかった」と振り返る。
62年に湯田ダム建設に伴う付け替え工事が完了し、66年「北上線」に改称。秋田新幹線開業準備に伴う田沢湖線工事時の96年には両県をつなぐ唯一の直通路線となる「秋田リレー号」が運行された。
北上市和賀町と西和賀町を結ぶ国道107号はこの10年で2度にわたる長期間通行止めとなる災害に見舞われ、北上線の重要性を再認識したという住民も少なくない。
(駅名は当時)
momottoメモ
(上)人と物 流れる動脈 鉱山が敷設の原動力に
(中)西和賀に欠かせぬ足 町と高校生 存続訴え
(下)「マイレール意識」が鍵 住民に積極利用の動き